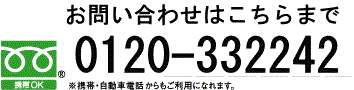労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針
(目的)
第一条 この指針は、事業者が労働者の協力の下に一連の過程を定めて継続的に行う自主的な安全衛生活
動を促進することにより、労働災害の防止を図るとともに、労働者の健康の増進及び快適な職場環境の
形成の促進を図り、もって事業場における安全衛生の水準の向上に資することを目的とする。
第二条 この指針は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)の規定に基
づき機械、設備、化学物質等による危険又は健康障害を防止するため事業者が講ずべき具体的な措置を
定めるものではない。
(定義)
第三条 この指針において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 労働安全衛生マネジメントシステム 事業場において、次に掲げる事項を体系的かつ継続的に実施
する安全衛生管理に係る一連の自主的活動に関する仕組みであって、生産管理等事業実施に係る管理
と一体となって運用されるものをいう。
イ 安全衛生に関する方針(以下「安全衛生方針」という。)の表明
口 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置
ハ 安全衛生に関する目標(以下「安全衛生目標」という。)の設定
二 安全衛生に関する計画(以下「安全衛生計画」という。)の作成、実施、評価及び改善
二 システム監査 労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置が適切に実施されているかど
うかについて、安全衛生計画の期間を考慮して事業者が行う調査及び評価をいう。
(適用)
第四条 労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置は、事業場を一の単位として実施すること
を基本とする。ただし、建設業に属する事業の仕事を行う事業者については、当該仕事の請負契約を締
結している事業場及び当該事業場において締結した請負契約に係る仕事を行う事業場を併せて一の単位
として実施することを基本とする。
(安全衛生方針の表明)
第五条 事業者は、安全衛生方針を表明し、労働者及び関係請負人その他の関係者に周知させるものとす
る。
2 安全衛生方針は、事業場における安全衛生水準の向上を図るための安全衛生に関する基本的考え方を
示すものであり、次の事項を含むものとする。
一 労働災害の防止を図ること。
二 労働者の協力の下に、安全衛生活動を実施すること。
三 法又はこれに基づく命令、事業場において定めた安全衛生に関する規程(以下「事業場安全衛生規
程」という。)等を遵守すること。
四 労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置を適切に実施すること。
(労働者の意見の反映)
第六条 事業者は、安全衛生目標の設定並びに安全衛生計画の作成、実施、評価及び改善に当たり、安全
衛生委員会等(安全衛生委員会、安全委員会又は衛生委員会をいう。以下同じ。)の活用等労働者の意
見を反映する手順を定めるとともに、この手順に基づき、労働者の意見を反映するものとする。
(体制の整備)
第七条 事業者は、労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置を適切に実施する体制を整備す
るため、次の事項を行うものとする。
一 システム各級管理者(事業場においてその事業の実施を統括管理する者及び生産・製造部門、安全
衛生部門等における部長、課長、係長、職長等の管理者又は監督者であって、労働安全衛生マネジメ
ントシステムを担当するものをいう。以下同じ。)の役割、責任及び権限を定めるとともに、労働者
及び関係請負人その他の関係者に周知させること。
ニ システム各級管理者を指名すること。
三 労働安全衛生マネジメントシステムに係る人材及び予算を確保するよう努めること。
四 労働者に対して労働安全衛生マネジメントシステムに関する教育を行うこと。
五 労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置の実施に当たり、安全衛生委員会等を活用す
ること。
(明文化)
第八条 事業者は、次の事項を文書により定めるものとする。
一 安全衛生方針
二 システム各級管理者の役割、責任及び権限
三 安全衛生目標
四 安全衛生計画
五 第六条、次項、第十条、第十三条、第十五条第一項、第十六条及び第十七条第一項の規定に基づき
定められた手順
2 事業者は、前項の文書を管理する手順を定めるとともに、この手順に基づき、当該文書を管理するも
のとする。
(記録)
第九条 事業者は、安全衛生計画の実施状況、システム監査の結果等労働安全衛生マネジメントシステム
に従って行う措置の実施に関し必要な事項を記録するとともに、当該記録を保管するものとする。
(危険性又は有害性等の調査及び実施事項の決定)
第十条 事業者は、法第二十八条の二第二項に基づく指針に従って危険性又は有害性等を調査する手順を
定めるとともに、この手順に基づき、危険性又は有害性等を調査するものとする。
2 事業者は、法又はこれに基づく命令、事業場安全衛生規程等に基づき実施すべき事項及び前項の調査
の結果に基づき労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を決定する手順を定めるとともに、
この手順に基づき、実施する措置を決定するものとする。
(安全衛生目標の設定)
第十一条 事業者は、安全衛生方針に基づき、次に掲げる事項を踏まえ、安全衛生目標を設定し、当該目
標において一定期間に達成すべき到達点を明らかとするとともに、当該目標を労働者及び関係請負人そ
の他の関係者に周知するものとする。
一 前条第一項の規定による調査結果
二 過去の安全衛生目標の達成状況
(安全衛生計画の作成)
第十二条 事業者は、安全衛生目標を達成するため、事業場における危険性又は有害性等の調査の結果等
に基づき、一定の期間を限り、安全衛生計画を作成するものとする。
2 安全衛生計画は、安全衛生目標を達成するための具体的な実施事項、日程等について定めるものであ
り、次の事項を含むものとする。
一 第十条第二項の規定により決定された措置の内容及び実施時期に関する事項
二 日常的な安全衛生活動の実施に関する事項
三 安全衛生教育の内容及び実施時期に関する事項
四 関係請負人に対する措置の内容及び実施時期に関する事項
五 安全衛生計画の期間に関する事項
六 安全衛生計画の見直しに関する事項
(安全衛生計画の実施等)
第十三条 事業者は、安全衛生計画を適切かつ継続的に実施する手順を定めるとともに、この手順に基づ
き、安全衛生計画を適切かつ継続的に実施するものとする。
2 事業者は、安全衛生計画を適切かつ継続的に実施するために必要な事項について労働者及び関係請負
人その他の関係者に周知させる手順を定めるとともに、この手順に基づき、安全衛生計画を適切かつ継
続的に実施するために必要な事項をこれらの者に周知させるものとする。
(緊急事態への対応)
第十四条 事業者は、あらかじめ、労働災害発生の急迫した危険がある状態(以下「緊急事態」という。)
が生ずる可能性を評価し、緊急事態が発生した場合に労働災害を防止するための措置を定めるとともに、
これに基づき適切に対応するものとする。
(日常的な点検、改善等)
第十五条 事業者は、安全衛生計画の実施状況等の日常的な点検及び改善を実施する手順を定めるととも
に、この手順に基づき、安全衛生計画の実施状況等の日常的な点検及び改善を実施するものとする。
2 事業者は、次回の安全衛生計画を作成するに当たって、前項の日常的な点検及び改善並びに次条の調
査等の結果を反映するものとする。
(労働災害発生原因の調査等)
第十六条 事業者は、労働災害、事故等が発生した場合におけるこれらの原因の調査並びに問題点の把握
及び改善を実施する手順を定めるとともに、労働災害、事故等が発生した場合には、この手順に基づき、
これらの原因の調査並びに問題点の把握及び改善を実施するものとする。
(システム監査)
第十七条 事業者は、定期的なシステム監査の計画を作成し、第五条から前条までに規定する事項につい
てシステム監査を適切に実施する手順を定めるとともに、この手順に基づき、システム監査を適切に実
施するものとする。
2 事業者は、前項のシステム監査の結果、必要があると認めるときは、労働安全衛生マネジメントシス
テムに従って行う措置の実施について改善を行うものとする。
(労働安全衛生マネジメントシステムの見直し)
第十八条 事業者は、前条第一項のシステム監査の結果を踏まえ、定期的に、労働安全衛生マネジメント
システムの妥当性及び有効性を確保するため、安全衛生方針の見直し、この指針に基づき定められた手
順の見直し等労働安全衛生マネジメントシステムの全般的な見直しを行うものとする。